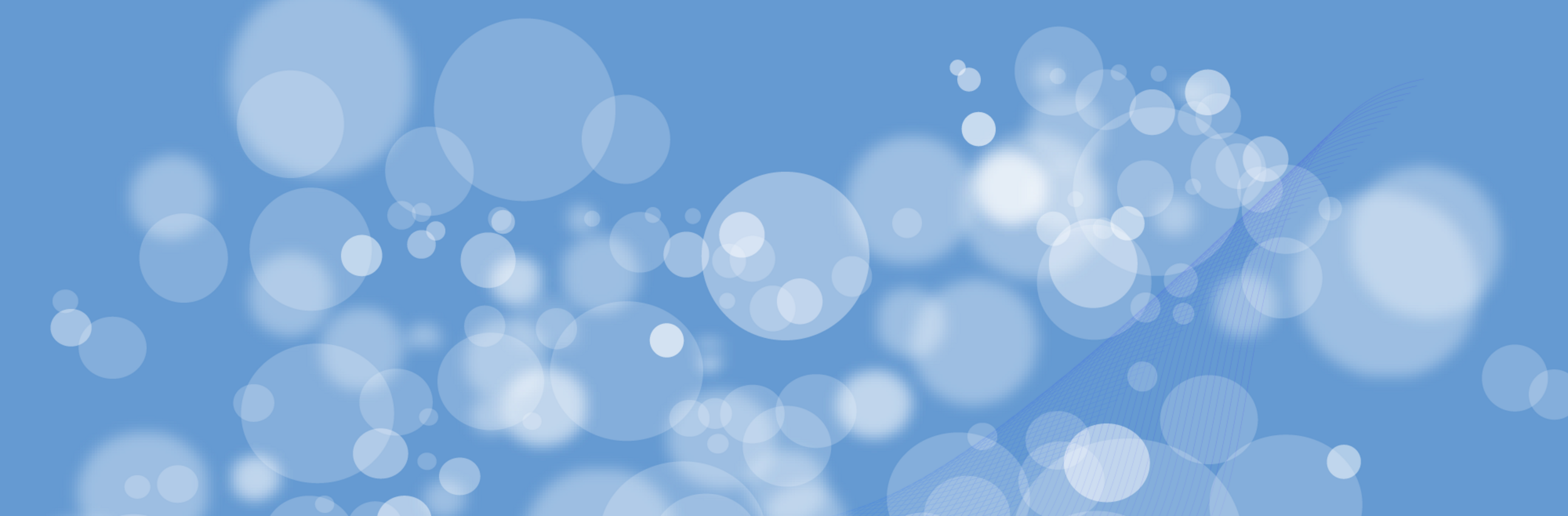
動的光散乱では、粒子からの散乱光強度の時間変化を解析することで、粒子のブラウン運動の速度を計測し、粒子径を測定しました。 これとは対照的に、散乱光強度の時間平均から粒子や分子の分子量を計測する、静的光散乱(Static Light Scattering、SLS)という手法があります。 静的光散乱の中にもいくつか手法が分かれていますが、ここではその中のデバイプロット法を用いた分子量測定について説明します。
デバイプロット法では、サンプルの濃度を変えながら、ある一つの検出角度における散乱光強度を計測します。 散乱光強度と分子量Mはレイリーの理論で関係づけられています。
K⋅CRa=1M+2A2
光学定数K、サンプル濃度C、レイリー比Ra、第2ビリアル係数A2
光学定数Kは下式で定義されています。
K=\frac{2π^2n^2}{N_A{\lambda}^4}\left(\frac{{\partial}n}{{\partial}c}\right)^2
分散媒の屈折率n、アボガドロ定数NA、レーザー波長λ、サンプルの示差屈折率∂n/∂c
縦軸にKC/Ra、横軸に濃度Cのプロット(デバイプロット)を行うと、切片の逆数から分子量を測定することができます。
分子量に加え、デバイプロットの傾きから第2ビリアル係数A2も算出されます。 A2は分子と溶媒の親和性度合いを表し、A2の値が小さいほど親和性が低いため、分子間の引力が強い状態を表します。
測定方法は、サンプルの濃度を変えながら散乱光強度を計測するというシンプルな内容ですが、この手法を用いることで 分子量を測定することができます。
ナノ粒子解析装置 nanoPartica SZ-100V2と典型的な測定例
nanoPartica SZ-100V2の光学系を下図に示します。 セル中の試料にレーザーを照射し、散乱角90°に配置した側方検出器(PMT)で散乱光を検出します。
典型的な測定例
ポリスチレン標準試料の分子量を測定した結果を以下に示します。
| 測定結果 | |
|---|---|
| 分子量 | 95,000 |
| 第2ビリアル係数 | 5.7×10-4 |
| 測定結果 | |
|---|---|
| 分子量 | 860 |
| 第2ビリアル係数 | 4.0×10-4 |
このように、デバイプロット法を用いることで分子量を測定することができます。 また、第2ビリアル係数からサンプルの分散安定性も評価することができるので、最適な分散条件の探索に使うことができます。
There are no results for this filter combination!
HORIBAは、「Your Partner in Science」をテーマにオンラインセミナーで、各種分析の基礎やノウハウを紹介しています。皆様からのご視聴お申込みを心よりお待ち申し上げております。
粒子計測、蛍光X線分析、元素分析、分光分析、ラマン分光分析、蛍光分光分析、表面分析の基礎やノウハウを紹介したセミナー(アーカイブ動画)の一覧です。