大阪科学技術館
HORIBAブース「はかるとわかる・ はかる研究所」

「はかる」は、ヒトの感覚だけではわからないことをはっきりと数字に表す技術(ぎじゅつ)であり、地球環境(かんきょう)をもっとよくするため、そして、私たちの豊(ゆた)かなくらしの実現(じつげん)にはなくてはならないものです。
大阪科学技術館(おおさかかがくぎじゅつかん)(大阪市西区)内にあるHORIBA(ほりば)ブース
「はかるとわかる・はかる研究所」では、「はかるとわかる」をテーマに、
「はかる」装置(そうち)※1を使って遊びながらたのしく「わかる」を体験することができます。
どれだけ温度が上がったかな? どれだけぴかぴかかな? この砂(すな)のなかになにがあるのかな?
ヒトがさわっただけ、見ただけではよくわからないことも、
ほんまもん※2の装置で「はかる」とはっきり「わかる」ようになるよ!
大画面のゲームでは、こまっている人たちを「はかる」装置で助けるクエストにチャレンジしよう。
※1 装置(そうち)…ここでは、はかる機械(きかい)のことを「装置」と呼んでいます。
※2 ほんまもん…HORIBAが生まれた京都では「ほんまもん」という言葉がつかわれているよ。
「本物(ほんもの)」である、という意味だけではなく、人の心に感動やひらめきをあたえ、信頼(しんらい)できるものであるという意味がこめられているんだ。
1.温度をはかる
ヒトにはいろいろなセンサー※3があり、私たちの「皮ふ」は温度を感じることができます。
このコーナーでは、自分の手の感覚と本当のの温度にどれくらいの差があるのかを、ゲームを通して楽しく体験できます。
きみの手の温度センサーはどれだけ正確(せいかく)かな。
巨大(きょだい)温度計に手を入れてたしかめてみよう!
※3 センサー…ものを感じる部分のこと
ぴったり温度を当ててみよう!

ゲームのやり方
➀巨大温度計のあなに手を入れる。
手の表面の温度が画面に表示(ひょうじ)されるよ。
②赤いきのこのかたちのボタンをおす。
温かい風がでてきて手が温められるよ。
③手の温度が2℃上がったと感じたときに、
もう一度きのこのかたちのボタンをおす。
どれだけ温度が上がったか 画面に表示されるよ。
放射温度計のしくみ
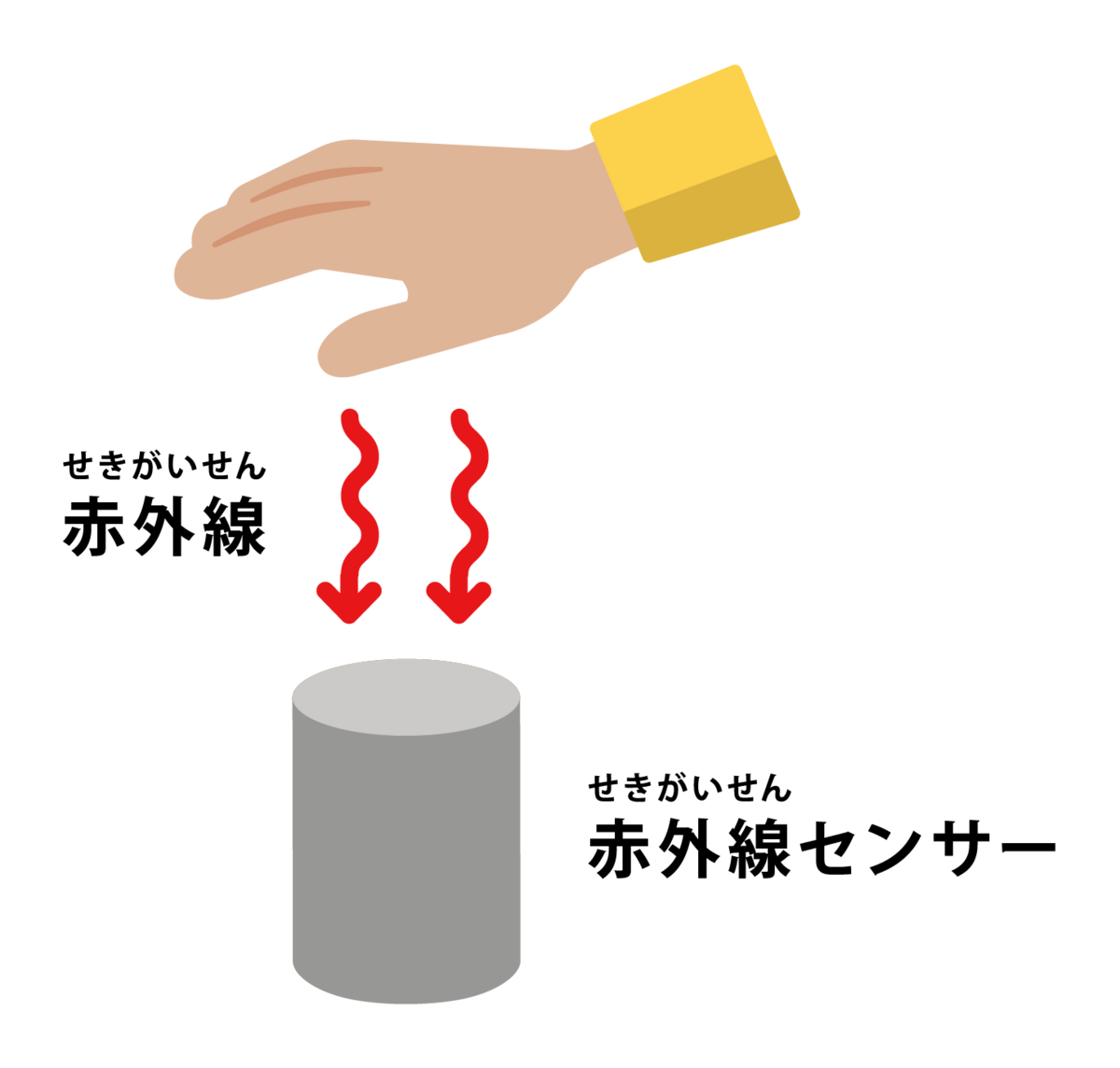
このゲームには放射温度計という装置が使われています。
放射温度計は、あらゆるものからでている赤外線(せきがいせん)をキャッチすることで、温度をはかることができます。
放射温度計について、くわしくはこちら
赤外線と放射温度計
2.ぴかぴかをはかる
わたしたちの「目」もセンサーの一つです。目の能力(のうりょく)のひとつに、ものがどれだけぴかぴかであるかをはかることができます。
しかし、そのぴかぴか度は見る人によって差があるのはもちろん、その時の周りの明るさによっても変わるため、正しくに表すことがむずかしいのです。
そんなあいまいなぴかぴか度(「光沢度(こうたくど)」ともいいます)を数字ではっきりと表すことができるのが光沢計(こうたくけい)とよばれる装置です。
ぴかぴかをはかってみよう!

こちらのコーナーには、フライパン、お皿、スマートフォン、タイヤ、学校のつくえ、ランドセルなど、みんなの身近にある20種類以上のものがあります。
光沢計を使っていろいろなもののぴかぴか度をはかってみよう。
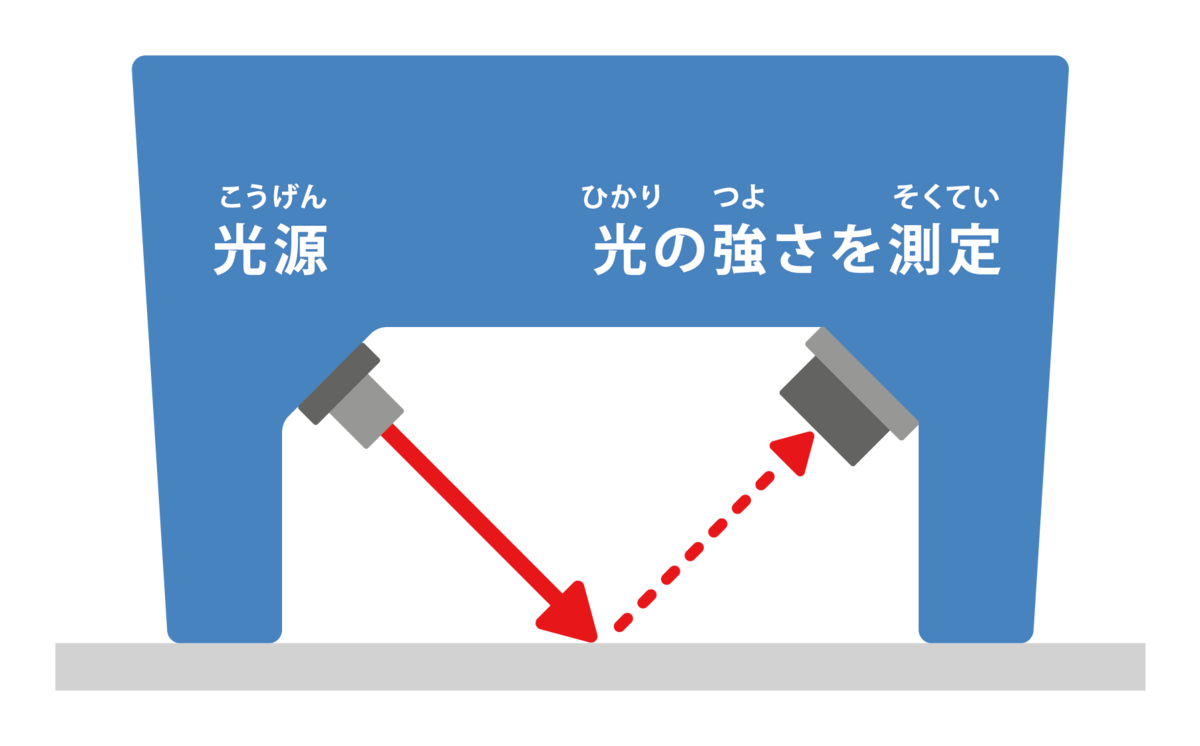
光沢計のしくみ
装置の底から出る光が、測定したいものの表面で反射(はんしゃ)され、
その反射する光の強さからぴかぴか度(光沢度)をはかります。
光沢計について、くわしくはこちら
光沢計
砂(すな)のなかのマイクロプラスチックを見てみよう!

この巨大顕微鏡を使うと、砂のなかのプラスチックだけが赤く光り、見ることができます。
山から海へと、水が流れるまでの間にある砂(➀山の砂、②川の上流の砂、③川の下流の砂、④海岸の砂)のなかにはマイクロプラスチックがふくまれているかな。
まちのなかの砂(⑤駐車場(ちゅうしゃじょう)の砂、⑥公園の砂)はどうだろう?
巨大顕微鏡をのぞいて、見てみよう!
マイクロプラスチックについて、くわしくはこちら
マイクロプラスチック分析
4.ホリバ クエストに挑戦(ちょうせん)!

みんなの周りにあるもののほとんどは、「こんなものがあったらいいな、助かるな、便利になるな」と思う人がいたから、つくられてきました。
「はかる」装置も同じで、こまっているだれかのため、だれかの役にたちたい!と思って、生まれてきたんだよ。
ホリバ クエストでは、こまっている人たちのなやみごとを聞き、みんなの問題を解決していくゲームです。
みんなもはかる装置のプロ、「ホリバリアン」になって、町の人たちを助けるお手伝いをしましょう!
こまっている人を「はかる」装置でたすけよう!
ゲームのやり方
➀3つのエリア(都市エリア、工場エリア、自然エリア)の中から、一つを選ぶ。
②選んだエリアの中で、こまっている人々のなやみごとを聞きます。
③画面に登場するホリバリアン(「はかる」のエキスパート)の意見を聞きながら、一番良いと思う解決方法を選ぶ。
④より効果のある方法を選べば多くの得点がもらえるよ。
大阪科学技術館
場所 大阪市西区靭本町1丁目8-4
入館料 無料
開館時間 10:00~17:00(日・祝は16:30閉館)
休館日はHPよりご確認ください。
大阪科学技術館公式サイト
