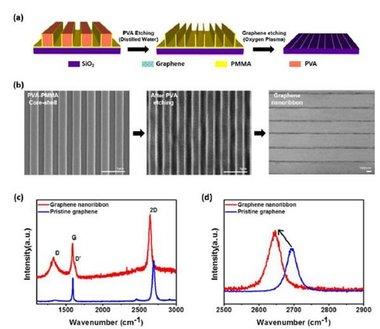*HORIBA Instruments Incorporated
ラマン分光法は1960年代初頭から半導体材料の分析に用いられてきた。当時は可視レーザーが利用できるようになり,ラマン測定の励起光源として標準的に使われるようになった時期である。1970年代半ばにはラマン顕微鏡が開発され[1],集積回路の発展に伴って,デバイスの性能解析などにつながる材料の特性評価の分野で重要な位置を占めるようになった。その典型例がシリコン半導体への応用であり,応力測定,p型ドーピング(高濃度),ポリシリコン中の結晶サイズ,配向性評価,不純物同定などが行われた。化合物半導体では合金組成や様々な種類のドーピング,表面空乏層の深さに影響を与える表面電解など,さらに多くの特性が評価されるようになった。光が材料に浸透する深さは波長に依存するため,励起レーザーの波長を調整することによって材料表面から深さ方向に異なる位置の分析が可能になり,表面空乏層の特性をバルク特性と区別して評価できるようになった。本稿ではこれまでの様々な評価とその効果についてレビューし,次世代半導体デバイスとして開発されているワイドバンドギャップ半導体においてどのように適用できるのかを提案する。また,ナノスケールでの測定や集積回路における光集積化についても解説する。