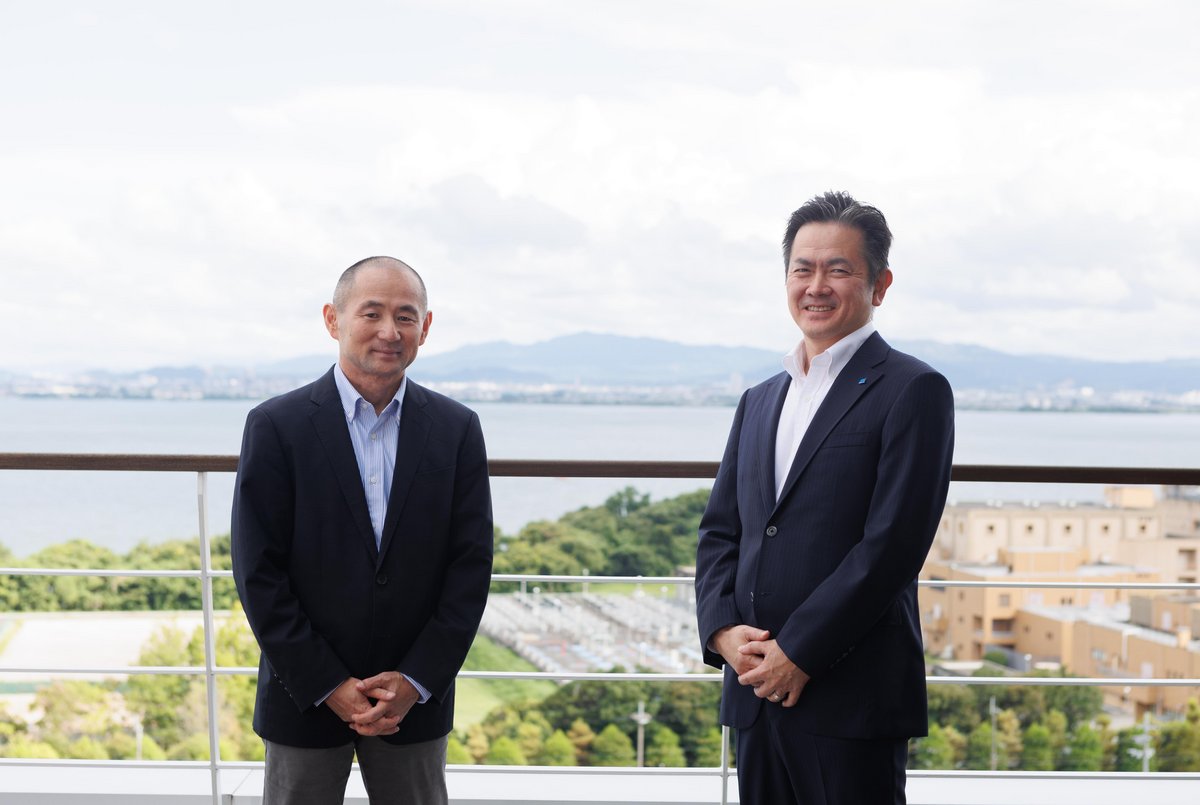チャレンジ精神で新たな事業領域の開拓を進めるHORIBA。共同研究のパートナーである東京大学・一杉太郎教授と堀場製作所の中村博司執行役員CTOが、社是「おもしろおかしく」をキーワードに語り合った。
チャレンジ精神で新たな事業領域の開拓を進めるHORIBA。共同研究のパートナーである東京大学・一杉太郎教授と堀場製作所の中村博司執行役員CTOが、社是「おもしろおかしく」をキーワードに語り合った。
一杉 創業者である堀場雅夫さんの著書を拝読しました。非常に興味深く読ませていただきました。創業者のお父様は研究者だったのですね。
中村 堀場信吉先生といいます。信吉先生は京都帝国大学(現京都大学)の出身で、皆さんにはあまり知られていないことですが浪速大学~大阪府立大学(現大阪公立大学)の第2代学長でした。京都帝国大学理学部で教授をされていた時に、音楽部の部長もされていたようで、当時は戦争中で制約もありましたが、大変熱心に活動されていました。また、京都市立音楽短期大学(現京都市立芸術大学音楽学部)の初代学長にも就任されています。住友総本店(現在の住友グループ)の銅の精錬所で亜硫酸ガスの煙害が発生したことがあり、それを解決する方法を堀場信吉先生に住友総本店が相談したことがあります。それをきっかけに彼らはドイツから「ハーバー・ボッシュ法」を導入しました。ハーバー・ボッシュ法でアンモニアを合成し、それを硫安(硫酸アンモニウム)にして肥料にするというものです。それをきっかけに住友総本店は堀場信吉先生の研究を援助し、その研究費でドイツのライプツィヒ大学やオランダのアムステルダム大学などに留学されていたこともありました。
一杉 私も専門が化学なので大変親近感がわきます。
中村 HORIBAの中で従業員を表彰する賞があり、技術系の最高位の賞は堀場信吉賞といいます。私も10年くらい前に頂きました。
一杉 研究者、技術者を大切にしている御社の社風がよくわかりました。先ほど「Joy and Fun for All」という標語があると聞きました。私は大学時代にラグビー部に所属していました。ラグビーでいうと「一人はみんなのために、みんなは一人のために(one for all, all for one)」の精神が有名です。この言葉は、「一人はみんなのために、みんなは一つの目的のために」とも解釈されており、最近の言葉でいうと「ワンチーム」ということになります。創業者の堀場雅夫さんも中高校生時代にラグビーをされていました。チームワークを重視するという点では研究もラグビーも同じです。
中村 社是は「Joy and Fun(おもしろおかしく)」ですが、2023年に創立70周年を迎えるにあたり、Our Future Projectを立ち上げ、我々のビジョン、ミッション、バリューは何かを考えました。世界7カ国から20人前後のコアメンバーを選び、様々なワークショップを経て、HORIBAが100周年を迎える2053年のビジョンを、「Joy and Fun for All(おもしろおかしくをあらゆる生命へ)」と定めました。今までおもしろおかしくは自分たちだけのものでしたが、それを地球上のみんなが分かち合い、共に成長することを表しています。
一杉 いいですね。「生命へ」とは、「地球上のみんな」という意味があったのですね。
中村 「Joy and Fun for All」とはまさしく「one for all」のことです。
一杉 本当にそうですね。そこから来ているのですね。非常に興味深いです。
一杉 そう感じます。堀場雅夫さんが「おもしろおかしく」を重視したのには、ご自身の小学校時代の原体験があったからではないかと私は推測します。京都にある師範学校の附属小学校に在籍されていたときのエピソードが書籍に記されています。放課後に教育実習生から、雅夫さんが好きだった理科を親身に教えてもらっていました。そこで科学への興味が培われたのだと思います。内側から湧き上がるモチベーション、そして、好奇心が刺激される環境がありました。「おもしろおかしく」というのは、やらされ仕事ではなく楽しんで、好奇心を持って仕事をすべしという思いから生まれたのだと考えています。
中村 そうですね。
一杉 好奇心に応じて仕事を進めることは非常に重要だと思います。大学でなぜ研究をするかというと、それは学生が好奇心を持っているからです。好奇心に基づいた研究はやらされ仕事ではないので、最大の教育効果が出るのですね。学生自ら学びを深めます。「ここが知りたい」「これは何だろう」という好奇心が刺激される環境があることは素晴らしいことです。
中村 創業者は完全週休3日にして、残りの4日間は昼夜問わず好きな研究に没頭する、寝泊まりできる研究所を琵琶湖の畔に作りたかったようです。モチベーションを持って新しいことにチャレンジできる環境を作りたいという思いが根底にありました。その思いは、2016年5月に稼働したびわこ工場に息づいています。
一杉 私が研究を始めた頃は高温超伝導が注目され、私も好奇心から研究に没頭しました。まさにおもしろおかしく研究していました。今の時代においても、学生が没頭できるテーマを作り出していくことが、大学の教員である我々のミッションだと思っています。
中村 好奇心旺盛な学生さんが社会人となり会社に入ってきた時に、その好奇心を絶やさないようにするにはどうすればよいか、常に考えています。最近、あるトライアルを始めました。若手社員から自由に好きな研究テーマを公募します。それに予算を付けて、勤務時間内での研究を認めます。研究に充てられる時間は全体の仕事の10%程度ですが、通常勤務を早く終わらせれば、その分、自分の研究時間を増やせます。自分の裁量で研究ができます。
一杉 大変すばらしい試みですね。自分の視野が広がりますし、最終的には今の仕事にも活きてくるのは確実です。
一杉 高温超伝導体の発見がきっかけでした。1986年に発見され、その結果、世の中が大きく変わるという話がありました。エネルギー問題も解決できるといわれていました。そのように社会に大きなインパクトを与える新しい物質・材料は面白いと思ったのです。今も研究室で固体材料の研究を進めており、私の夢は室温超伝導体の発見です。現在の超伝導体は冷却することが必要です。室温超伝導体が実現すれば電力も貯蔵できますし、エネルギーを損失なく輸送できます。現在、建設中のリニアモーターカーは超伝導状態にするために冷却装置が必要ですが、室温超伝導体が実用化できればその必要もなくなります。超低消費電力メモリーや演算素子も実現するでしょう。新物質や新現象の発見により、世の中に貢献したいという夢を持ち続けて研究を続けています。
中村 先生の研究施設を拝見してユニークだなと思うのは、半導体のプロセスで使われる原子レベルの成膜技術を、電池材料など機能性材料の開発に取り込んでおられる点です。これにより新しい発見、今までとは異なる特性が生まれるのだと思います。
一杉 半導体技術の進歩で原子レベルでの物質の構造制御が可能になりました。表面や界面の研究は非常に重要です。私は高度な成膜技術を持っていましたのでそれを電池の界面研究に適用しました。研究者として世界で自分にしかできないことをするのが非常に重要です。これがおもしろおかしく研究するということです。異分野を融合することにより、私自身のオリジナリティが高い研究にチャレンジしています。
一杉 研究で必要なのは、まず「測る」ということです。理解するためには測る必要がある。HORIBAさんの分析装置は非常に優秀で重要です。測るという行為は、単にスペクトルを得て終わりではありません。データの質を上げるだけではなく、複数の装置をシステム化し、そのデータが何を意味するかを総合的に判断することが期待されます。
中村 元々、我々は5つのセグメントで事業展開してきましたが、それぞれの事業が持つ技術を他の事業に展開するのが難しいという課題がありました。そこで、2024年2月に策定した新しい中長期経営計画「MLMAP2028」では、5つのセグメントを「エネルギー・環境」「バイオ・ヘルスケア」「先端技術・半導体」の3つのフィールドに再編しました。事業と開発のレイヤーを分けて、開発部門が持っている様々な技術を融合すれば先生のいうチャレンジが可能になります。例えば、自動車開発のプロセス制御技術と、理化学機器の材料解析技術を融合した燃料電池製造プロセス監視技術など、新しい答えが出てきています。技術を融合することで、今まで提供できなかった価値を提供できるようになります。
一杉 そうですね。先ほどお話しした半導体と電池もまったく異なる分野のように思われますが、その異なる分野の技術を組み合わせることにより、新しいことが可能になります。測る技術をコアに、そこにシステム化やデータ活用をうまく組み合わせると、トータルなソリューションになると期待しています。
一杉 ルーティンワークばかりやっていても、おもしろおかしくないですよね。人工知能(AI)ロボットシステムを導入し、研究者をルーティンワークから解放し、おもしろおかしく研究ができる環境を整えることが目的です。化学や材料の知識のほか、デジタル、ロボット分野などの知識も活用します。世界ではデジタル化が非常に速い勢いで進んでいます。皆さんもそれを感じているのではないでしょうか。私は、日本の遅れが非常に心配です。幸い日本にはHORIBAさんのような優秀な計測機器メーカーがある。一緒に新しい研究開発の姿を作っていければと思っています。
中村 自動車産業に関連する研究開発設備の設計に長く携わってきましたが、日本でDXが進まないのは、産業構造的な問題が背景にあるからだと思います。例えば、半導体業界では、かなり以前から設計に特化したファブレスと、製造技術に特化したファウンドリに明確に分かれ水平分業が進んでいます。製造装置メーカーは製造装置の研究開発に特化でき、グローバルで様々な設備に対するノウハウが水平展開されています。そうすると、DXの横展開が可能になります。同じようなことは、医薬品の開発製造を受託する機関(CDMO)が出てきた製薬業界でも起こっています。日本は昔から系列が強く、垂直統合が進みました。ある分野に特化した技術開発は有効ですが、グローバルで戦うには汎用的な技術が広がらないという問題が生じます。
一杉 縦割りになると視野が狭くなります。大学では化学、物理などと分野が決められ、縦割りになっています。例えば、複数の学位を取得できるダブルディグリーのような制度を充実させ、化学とコンピュータサイエンスというように異分野を融合させていけるような人材を増やしていく必要があると思います。デジタル技術を化学・材料分野や物理、計測に導入するために、人材育成が非常に重要な課題です。化学・材料を研究する学生が、デジタル技術、ロボット技術、システム化技術を体得する場を提供していきたいと思っています。
中村 我々も新しい研究分野に入っていこうとすると、社内で新しい知識を取り込んでいくのは簡単ではありません。そのような時は様々な大学や研究機関と共同研究、共同実験の場を作り、そこに社員が入り現場で経験してもらうことが重要だと思っています。
一杉 HORIBAさんは自動車触媒評価などの実験ラボをシステム化するという非常に優れた知見と技術を持っておられる。それを他の事業ドメインに展開できれば社会全体に貢献できます。
中村 MLMP2028では、自動車分野で培ったオートメーションやデータマネジメントのビジネスモデルを他の領域に広げていくことを戦略の一つに掲げています。また、我々の計測機器のほか競合メーカーの機器も含め、モジュールの実装を容易にするプラグアンドプレイを実装してきた経験を自動車以外の領域に展開したいと考えています。
「チャレンジ精神」「誠実と信頼」「卓越の追求」の3つが我々の掲げるバリューです。先生とは価値観を共有できます。価値観が合えばより良い結果が期待できます。大きなゴールをめざして、今後もご一緒できればと思います。
一杉 是非お願いします。共同研究は異分野融合のスタートとなります。チャレンジ精神で自分の殻を破り、おもしろおかしく研究を進めたいです。
一杉 最大の利点は研究開発スピードが加速することです。新材料を開発することを考えます。従来は、自分自身で物質合成しなければなりませんでした。しかし、自動・自律実験システム(デジタルラボ)が登場したことにより、そのシステムに指示を出すだけで物質合成できるようになります。従来は、その物質の特性評価に多大な時間がかかっていました。しかし、自動・自律実験システムを使うと、特性評価が迅速に完了します。そして、取得したデータ、計算、シミュレーションと組み合わせると、さらに、研究スピードを上げることができます。
今まで合成技術や特性評価技術を有する人のみが研究を進めることができました。しかし、デジタルラボを使うようになると、それら技術を有していなくても、アイディアがある人はだれでも研究を進められるようになります。これは、技術の民主化と言え、非常に重要なことです。それを進めるためには、ロボット技術や機械学習技術のさらなる進展が望まれます。また、実験は創意工夫によりどんどん変わっていきます。それに対応できるよう、実験システム全体がフレキシブルに対応できるような技術を開発していかなければならないと思います。
一杉 はい。実験技術を持っている特定の人のみが研究する時代から、皆で技術をシェアリングする時代を迎えています。
中村 その通りです。まさしく水平分業でつながっているということです。
一杉 技術のシェアリングが進めば、アイデアさえあれば誰でも研究に取り組むことができます。時間や場所の制約もなくなります。ただ、人間同士のコミュニケーションは非常に重要ですね。今回、初めてHORIBA BIWAKO E-HARBORを訪問し、担当者と話をさせていただきました。大変素晴らしい施設だと思います。しかし、E-HARBORに閉じこもることなく、皆さんにはどんどん外に出ていろいろな刺激を受けていただきたいです。そしてこのE-HARBORでの研究に新たな視点を持ち込むというサイクルが重要だと思います。
中村 先生には京都にある本社には何度か足を運んでいただいています。本社には科学セグメント、理化学機器を開発している部隊があり、先生とコミュニケーションを取らせていただいているのですが、E-HARBORに来ていただいたのは初めてのことです。E-HARBORでは自動車のオートメーションやシステムエンジニアリングの部隊がいます。我々が自動車でやっているビジネスモデルを理化学分野で展開していく上での橋渡し役を先生にお願いしたいと思っています。
一杉 科学のおもしろさや楽しさを若い人に積極的に伝え、人材を育てていきたいと思っています。おもしろおかしく研究を進めると、新しい発見が相次ぎます。すると科学が発展し、産業が潤います。それを見た子供が「自分もあのようになりたい」と思うようになり、科学の分野に入ってくる人が増えてきます。結果的によい循環が生まれます。
中村 創業者の堀場雅夫も、堀場厚会長も教育にはすごくこだわりがあり、STEAM教育に力を入れています。出前授業で機器を使ってマイクロプラスチックを計測したり、放射線モニターで自然界の放射線量を測ってみたりしています。大学での研究については、社会実装につなげなければならないという意識が強すぎるように思います。自由でオリジナリティのある研究に注力する先生がいてもよいですし、そういう研究をサポートするために京都大学と共同で、技術革新を先導する若手の基礎研究者を支援する「HONMAMON(ほんまもん)共創研究」を2023年に立ち上げました。
一杉 実用を追い求めるだけではなく、好奇心に導かれる研究、さらには、原理原則をきっちりと理解するための研究もしっかり進めたいと思います。その点でも御社との今後の協業を楽しみにしています。
(インタビュー実施日:2024年8月)
※掲載内容および文中記載の組織、所属、役職などの名称はすべてインタビュー実施時点のものになります。
[写真左]
一杉 太郎(ひとすぎ たろう)
東京大学大学院 理学系研究科 化学専攻 教授 兼
東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 特任教授
[写真右]
中村 博司 (なかむら ひろし)
堀場製作所執行役員最高技術責任者(CTO)兼開発
本部長。1998年堀場製作所入社。2023年から現職。